信越線廃線区間をハイキングコースとして整備した「アプトの道」は、片道6キロ、往復で12キロあります。人の歩く速さはおおよそ時速4キロなので3時間用意しておけば間に合うはずだと雑な計算をしていましたが…。果たして見立て通りだったのでしょうか。
Timetable
東京 6:28発
高崎 7:18着
7:30発
横川 8:03着
12:05発?
軽井沢 12:39着??
横川での滞在時間は4時間ですが、おぎのやでゆっくり食べたり、ちょっと鉄道文化むらによりたい、ということで11時過ぎには戻るイメージです。

祝日ということもあり新幹線の改札まではご覧のように伽藍としていた。
朝6時に東京駅は、普段10時とかに目を覚ますぬるま湯大学生にとって、かなり厳しいものです。しかし新幹線の改札の方まで行くとそこそこ人が。私も数年すればこの人達の仲間入りです。
旅行で東京から高崎まで新幹線を使うというのもなんだか勿体ないような気がします。しかし横川での滞在時間を考えると必要不可欠な出費でした。

天皇誕生日ということもあって皇居見えないかなーと思っていましたが少なくとも北陸新幹線のホームからは全く見えません。見えたら「ハッピーバスデー天皇!!!」とか呟こうと思っていたのですが残念でした。
取り敢えず車内に入ります。

シートは長距離バスのようなデザインです。フッドレストはプラスチックのレール上に取り付けられており、身長に合わせて調整出来るようになっていました。少し壊れやすいような気もしますが、乗りやすいものになったことは間違いありません。

高崎からは在来線で移動です。横川には2012年と16年の2度訪れたことがありましたが、その時は115系のセミクロスシートに乗車してのことでした。2018年に115系による定期運行を終了してからは使用車両は全て211系のロングシート車(3000番台)に統一されています。
せっかく横川駅構内で駅弁を販売しているのにボックスシートで食べることが出来ないのは勿体ないような気もします。でもそのうちロングシートでも駅弁を普通に食べれられるようになるかもしれませんね。

8:03 横川駅
スケジュール通りの到着です。駅正面にある鉄道文化村もまだ開いていません。駅そのものはかなり小さくなってしまいましたが、駅の隣の駐車場スペースの広さから往時の様子を伺うことが出来ます。

横川駅ホームから線路跡らしきものが伸びています。
恐らくここには線路が敷かれていたのでしょう。碓氷鉄道文化村の中を経由して再びアプトの道脇にある廃線のレールと合流しています。

ここから熊ノ平までは6km。往復で12kmですので11時位には帰ってこられるはず。
文化村を左に見ながら進んでいきます。

この足場もかつてアプト時代に使われていたものと思われます。やはり足回りと縁のあるものですね。

朝早かったこともあったのでしょう、人は殆どいません。時たますれ違うのは専ら犬と一緒に散歩をされているような地元の方です。またもうかたっぽ側の廃線は線路が敷かれたままであり、それも現役の路線と見紛うほど整備されています。
そういや一箇所サルが集まっている所がありました。目を合わせ過ぎないようにサーっと通過します。
8:40 丸山変電所
丸山変電所は横軽の電化に伴い1912年に建造・設置された変電所跡です。現役の施設とも遜色ない状態ですが、裏に回ると少し様子が変わります。


寄生された生き物のようにボコッと無骨な建物がくっついています。なんだかこれ以外は廃墟らしからぬ様子ですが、それだけ丸山変電所が整備が行き届いているという事なのでしょうか?

この煉瓦の建物は2つに分かれていて、横川側の建物(先程の写真で大きく写っていた方)が送電などを行う蓄電池室で軽井沢側(今の写真)が変電用の機械室だったそうです。
2つの建物は写真の通り、ほぼ同じ形をしていることがわかります。
中に入ることは出来なさそうだったので10分程でコースに戻りました。

これは碓氷第一橋梁の写真ですが、柱に段差が作られているのがわかります。なんだか不安定なようにも見えてしまいますね。

旧線側は橋台を残すのみとなっていました。

まもなくして峠の温泉辺りに到着しました。ここで新線区間とアプトの道は分岐します。再び合流するのは熊ノ平ですが、それにしても随分と簡易的なバリケードです。

間もなくして最初のトンネルが出てきました。第一隧道です。

トンネルの上部が黒くなっているのは煤のせいなのでしょうか。少し煉瓦が取れている部分もあって保全の難しさを実感しながら不安を覚えさせられる所もあります。

反対側の坑口は煉瓦オンリーのように見受けられます。また反対の坑口が見えないことから分かる通りカーブしています。執筆している今振り返ってみるとこの隧道(1893年)と同時期に作られた伊納隧道(1897年)で扱われ方が大きく違う事を考えさせられます。どちらも都市からのアクセスが極端に悪いわけではないのですが…

トンネルを抜け第2橋梁を越えます。ここからすぐの第2隧道手前にあるベンチで一旦休憩です。軽食を取りましたが今から考えてみれば猿とかを道中で見かけていたのに不用心なことをしたと反省しています。

第2隧道を越えると碓氷湖です。
9:33 碓氷湖

ここら辺から慌て始めました。今往路の行程3分の2の所まで来ましたが、ここまで80分掛かっています。このままのペースならば熊ノ平まで更に40分かかります。更にめがね橋で一旦止まる時間を10分と考えて復路の出発が10時半となるわけですが、12時5分のバスに間に合うよう1時間台前半で降りなければなりません。
とはいえ引き返す訳にはいきません。めがね橋まではガシガシ移動していきます。

この時は目的地までの行程をトンネルの数で考えていました。今からすれば全く理にかなった考え方ではありませんが、熊ノ平までトンネルの数は全部で10本で碓氷湖の時点ではまだ2本目を通ったばかりです。これは碓氷第三隧道ですがこの位置から3・4・5が目視出来るこの状況は精神的にバフになりました。最もしっかり味わうことが出来たか否かが懸案なのは否定できませんが。

なにか写ってたらと思うと撮影出来なかった。
このまま第五隧道まで進んだ所で第3橋梁、めがね橋に到着しました。

9:50 めがね橋(碓氷第3橋梁)
熊ノ平までは1.3kmで、看板に書かれた所要時間は25分。引き返すか否か、はたまた軽井沢まで歩いちゃうか。頭の中に余裕などもうこれっぽっちも残っていません。取り敢えずめがね橋を下から見上げずに帰るのは無いので下に降りていきます。

ほぼ全てが煉瓦で出来ためがね橋。上の方がいかにも橋という感じが出ていますが、この橋の見どころは専ら下部の圧倒的な質量感を持った柱部分だと思います。

もうすこし近づいてから撮られたこの写真のほうが柱の大きさがわかりやすいかもしれません。奥と手前両方の看板からその大きさがわかってもらえると助かります。こうしてみると頭の中で思い描いていたものより少し重厚な感じがしました。
こうしているうちに少し落ち着いてきました。上に上がります。

上からは新線を奥の方で見ることができました。新線の方まで道は続いているようですが、時間がないのは勿論のことながら通行止めにしているのが見えたので再び降りるなんてことはしません。取り敢えず10時20分までに熊ノ平を目指して西進する。そしてもし引き返しても間に合わなかったらタクシーを呼ぶ事も視野に入れて最後まで進むことにしました。

第六隧道では横穴?から外が見えました。1年前に行った赤沢隧道を思い出します。(その時の記事はここから)

第6は500m程と少し長かったものの第7・8・9隧道は短く、横軽のバスに間に合うような気がしてきました。

そのまま最後の隧道まで来ました。なんだかこの隧道だけ斜めっているような気もしますが、当日は全く気づきませんでした。坑口の反対側はもう熊ノ平です。

10:18 熊ノ平信号場
なんとか時間内に到着すること出来ました。歩きながら25分にはここを出ることを決めます。

先程の写真にも写っていたこの白い建物は1937年に建造された熊ノ平変電所です。元々白く塗装サれていたことも大きいのでしょうが、先輩の丸山変電所よりもボロっとしています。個人的にはこの変電所も丸山変電所に負けないくらい大好きです。

奥にあるトンネルまでは近づくことが出来ませんでした。

1918年に発生した熊ノ平駅列車脱線事故で機関車が激突した場所である。
10時22分、撤退します。
バス発車20分前の11時45分を目指して下り始めました。

下ってみると明らかに坂道になっていることがわかります。上り坂の時は殆ど坂であることを視覚以外では実感できていませんでした。
膝に来ない位ですこぶる歩きやすいです。

サーキットみたいだな。オタクくんがいかにも好きそうな感じ。でもレースはヴァーチャルに留めておきましょう。
10:41 めがね橋
上りのほぼ1.5倍のペースで来ています。横川駅まで80分のペースでこれています。何とか間に合いそうです。

10:52 碓氷湖(第2隧道軽井沢側坑口前)

帰り道では観光客らしき人もちらほら見るようになりました。普通は7時に家を出て9時位に着くというのがよくある旅行ですよね。
しかし今回で言えば、一本後の列車(横川駅8:36着)にしていたら、最後まで歩くことはまず出来ませんでした。3時間で行けるだろうという考えがあまりにも詰めの甘いものでしたが、滞在時間を4時間取っておいたのは結果として良かったなと考えていました。(そもそもこの旅程全体が欲張りさんだったから起きたことではありますが)

11:40 横川駅
熊ノ平から75分。理想としていたタイムを上回る形で戻ってくることが出来ました。
流石に文化むらに入るのは無理があったので諦めましたが、せっかくなので同行者が行きたがっていたおぎのやの店舗へ向かいました。

祝日ということもあったのか店内で食事する人も少なくありませんでした。それにしても高齢者が多かったのですが、ハイキングで会わなかった人たちばかりだったのが少し気になりました。地元でのある種のコミュニティセンターみたいになっているのでしょうか。
流石に食事をするのは躊躇われたので釜飯を購入だけして駅前のバス停へ向かいます。

そして11時58分、無事バスに乗車することが出来ました。
~~~
結局の所そこまで焦る必要が無かったのかもしれませんが、単純計算でハイキングの行程を組み込むのはもう今回で最後になるでしょう。
それと熊ノ平から軽井沢までは横川までより近いのですが、歩道のスペースがなくオススメ出来ません。もしそのまま軽井沢まで抜けるならばオフシーズンを避けて横軽バスが旧道を通る時期に訪れるのが良いでしょう。何れにしてもめがね橋の大きさ、迫力には写真では伝えきれないものがあります。是非訪れてみてはいかがでしょうか。
参考資料
安中市教育委員会HPより http://www.annaka.ed.jp/sakamoto/diary/diary19/mrganebashi.pdf




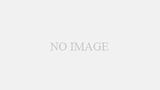

コメント